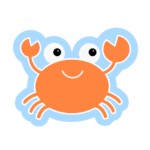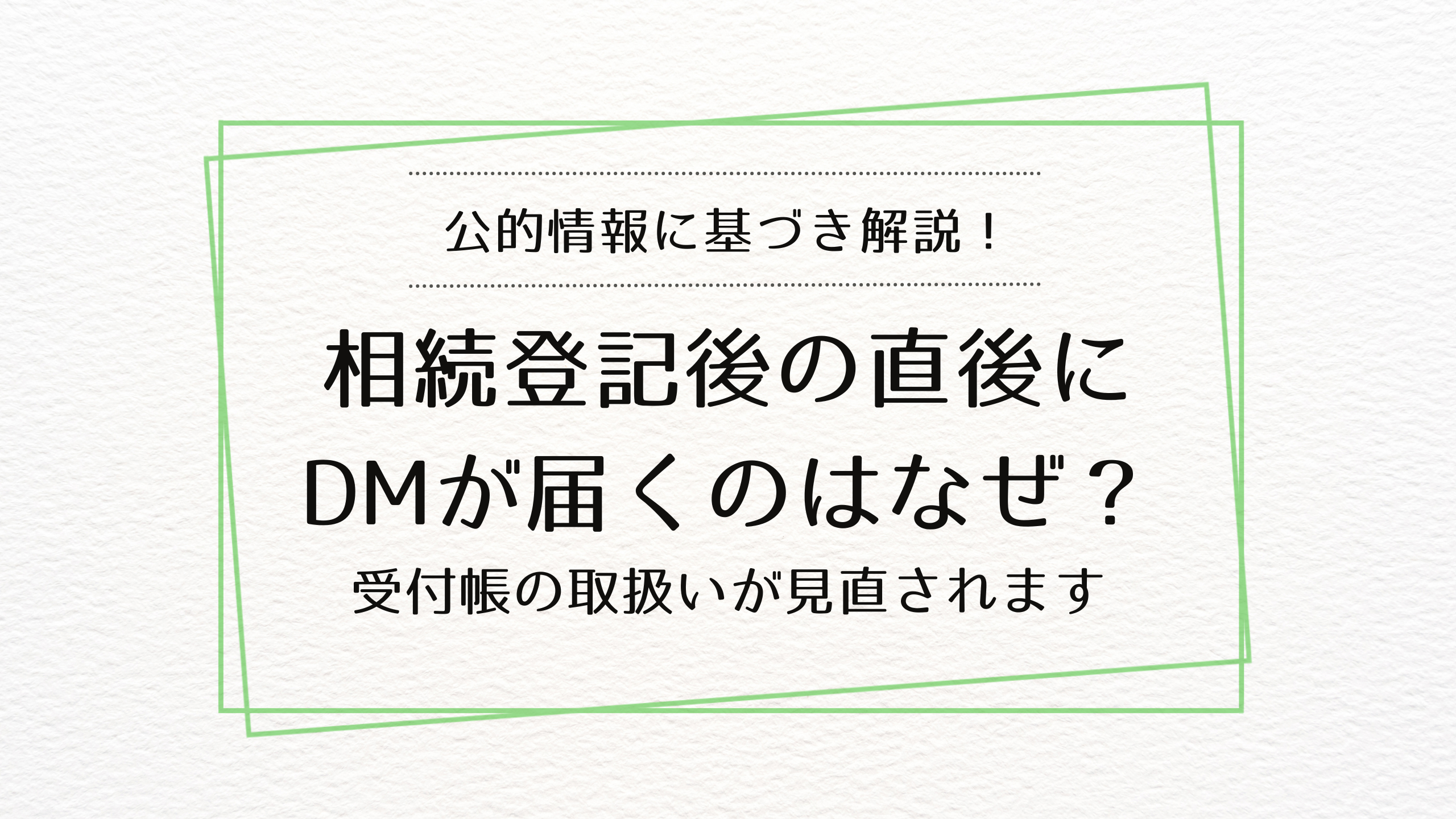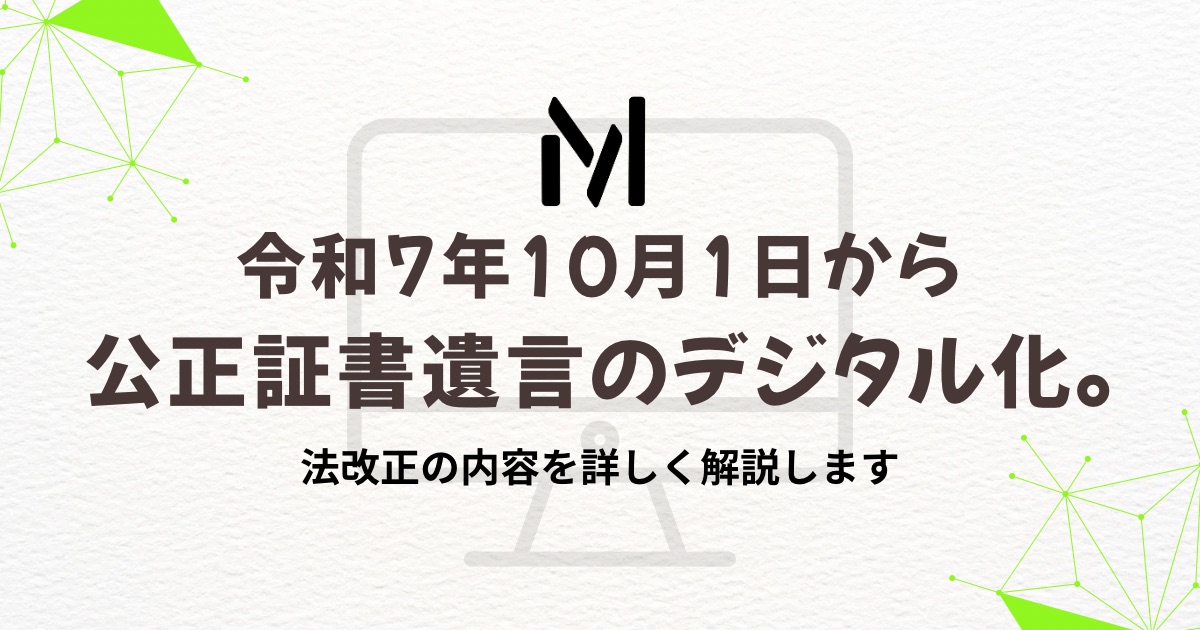預貯金債権は遺産分割の対象となるのか ―平成28年12月19日最高裁大法廷決定を踏まえて―
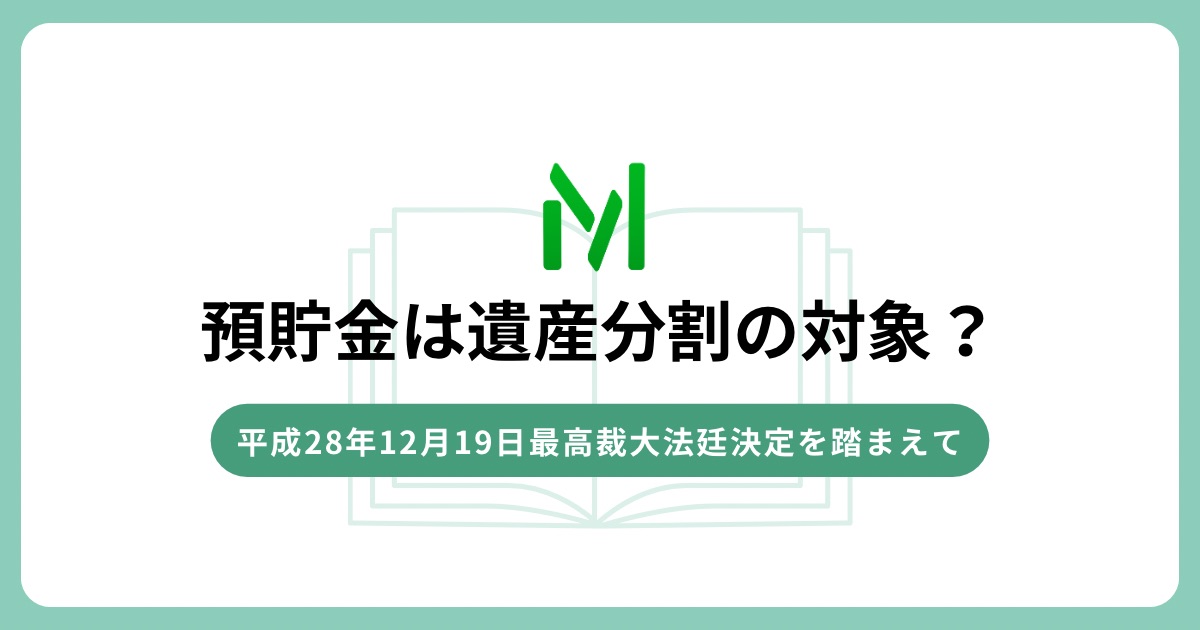
※本記事は、掲載時点で施行されている民法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに
遺産分割における預貯金債権の取扱いは、実務上長く議論が続いてきた重要テーマです。
かつて最高裁は「預貯金は可分債権であり、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割される」との立場を示しており(最判平成16年4月20日)、この解釈の下では、預貯金は各相続人が相続開始時点で単独債権として取得するものとされていました。
しかし、この運用では特別受益や寄与分による調整が働かず、結果として相続人間の不公平を招く事例も見られました。
こうした課題を背景に、その後の判例・立法の動きによって、預貯金債権の位置づけに変化が生じています。
では、この変化はどのようなものであったのかを見ていきましょう。
従来の最高裁の立場(最判平成16年4月20日)
平成16年判決は、昭和29年4月8日判決を踏襲し、次のように判断しました。
「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではない」
この結果、預貯金債権も可分債権とされ、遺産分割協議や審判の対象外とされていました。これは民法427条(分割債権及び分割債務)の原則論といえます。
判例変更の内容(最判平成28年12月19日大法廷)
では、ここからなぜ遺産分割の対象にされたのか、遺産分割の趣旨から見ていきましょう。
遺産分割制度の趣旨
遺産分割制度は、被相続人の権利義務を承継するにあたり、共同相続人間での実質的な公平を確保することを目的としています。
この目的からすれば、遺産分割ではできる限り幅広い財産を対象とし、特別受益や寄与分などを総合的に考慮して調整することが望まれます。
現金の調整機能と預貯金の評価
現金は、評価が容易で確実に換価できるため、分割困難な財産(不動産や株式など)を含む相続において調整機能を果たします。
最高裁は、この「調整機能」に着目し、預貯金も現金に近い性質を持つと評価しました。預貯金は確実かつ容易に換価でき、現金との差を意識させない財産として取り扱われています。
結論
最高裁は、普通預金・通常貯金・定期預金などの預貯金債権について、相続開始時に当然分割されるのではなく、遺産分割の対象とすると判示しました。
これにより、預貯金も含めた総合的な遺産分割が可能となり、相続人間の公平確保が図られることになりました。
民法909条の2の新設
平成28年大法廷決定を受け、2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法において民法909条の2が新設されました。
民法909条の2第1項
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権について、相続開始の時の債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額(法務省令で定める額を限度とする)までは、単独で行使することができる。
この結果、
- 一定額(1銀行につき150万円を限度)までは単独払戻し可能(葬儀費用などに充当できる)
- それを超える部分は遺産分割の対象
という二段構えの制度が確立しました。
まとめ
平成28年大法廷決定により、預貯金債権は原則として遺産分割の対象とされることになり、その後の民法改正で明文規定が設けられました。
現行実務では、生活費等の必要に応じた一部払戻しを認めつつ、それ以外は遺産分割で総合的に調整する仕組みが採られています。
この制度により、相続人間の公平と実務上の利便性の両立が図られています。
題材判例
最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定(平成27年(許)第11号、遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。