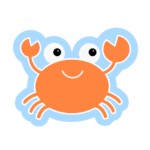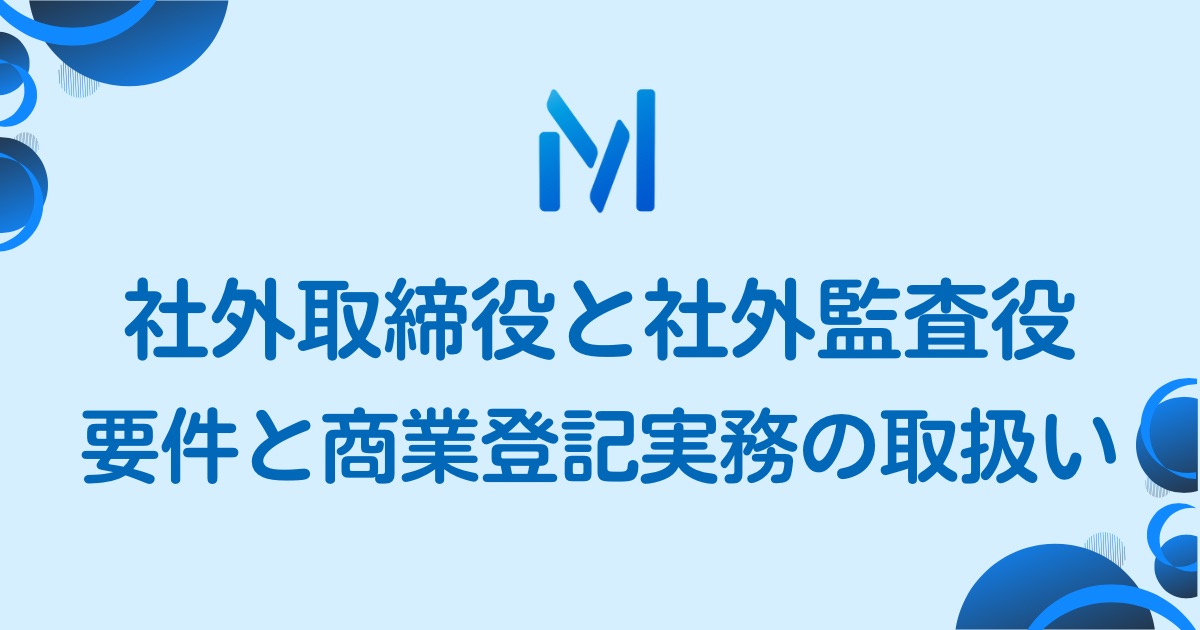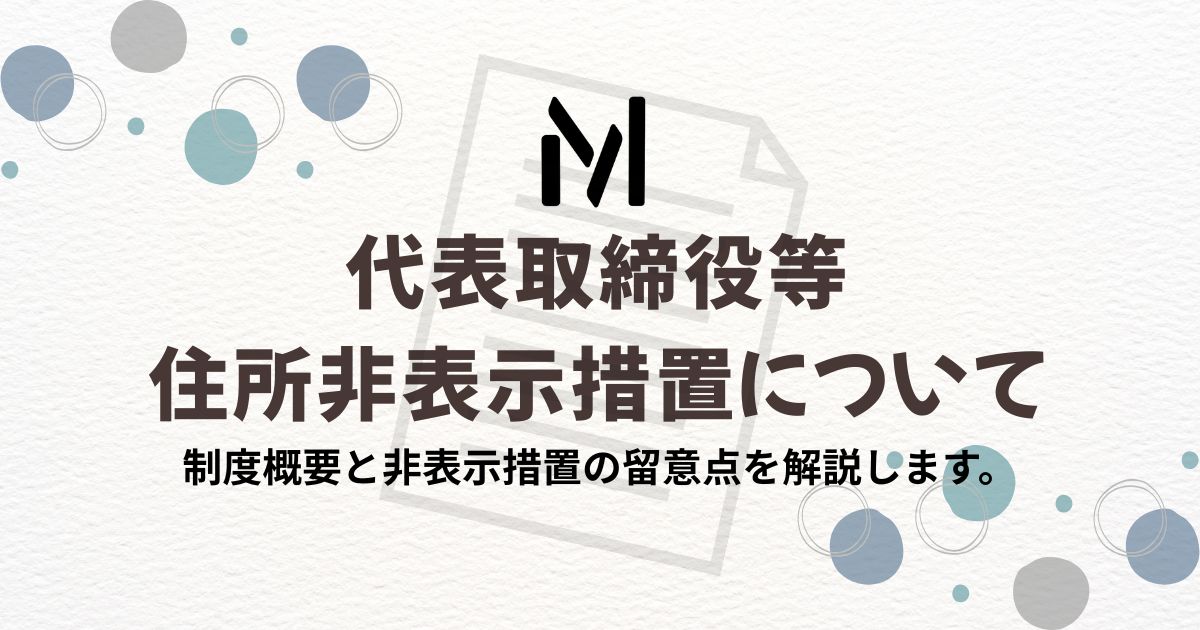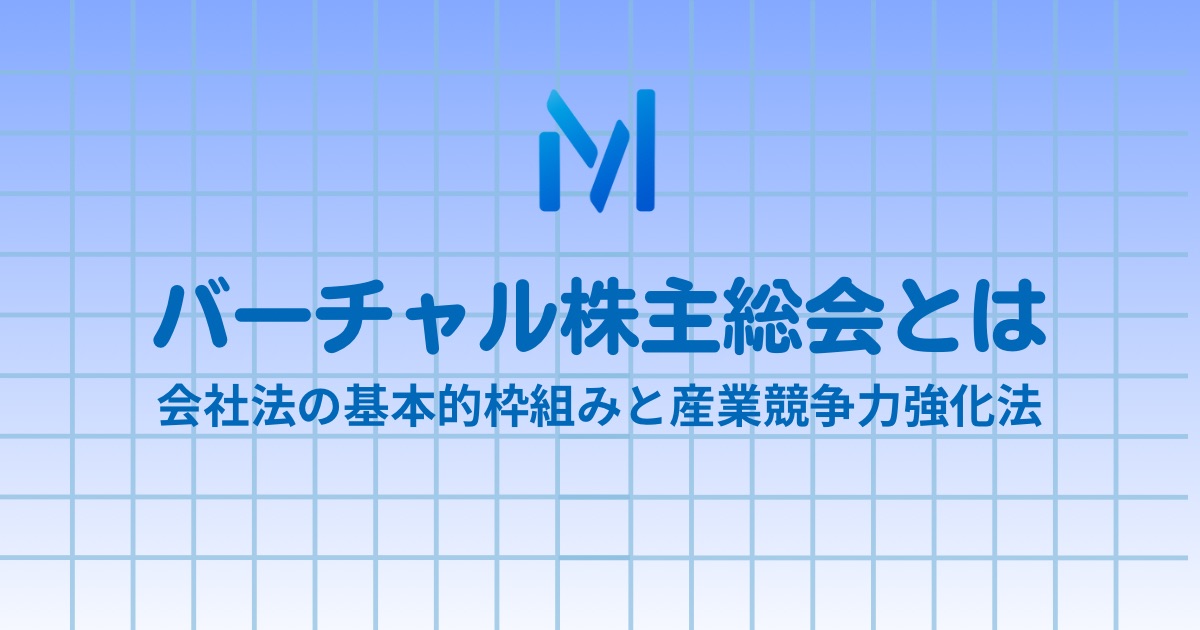相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定めー会社乗っ取りのリスクと防止策ー
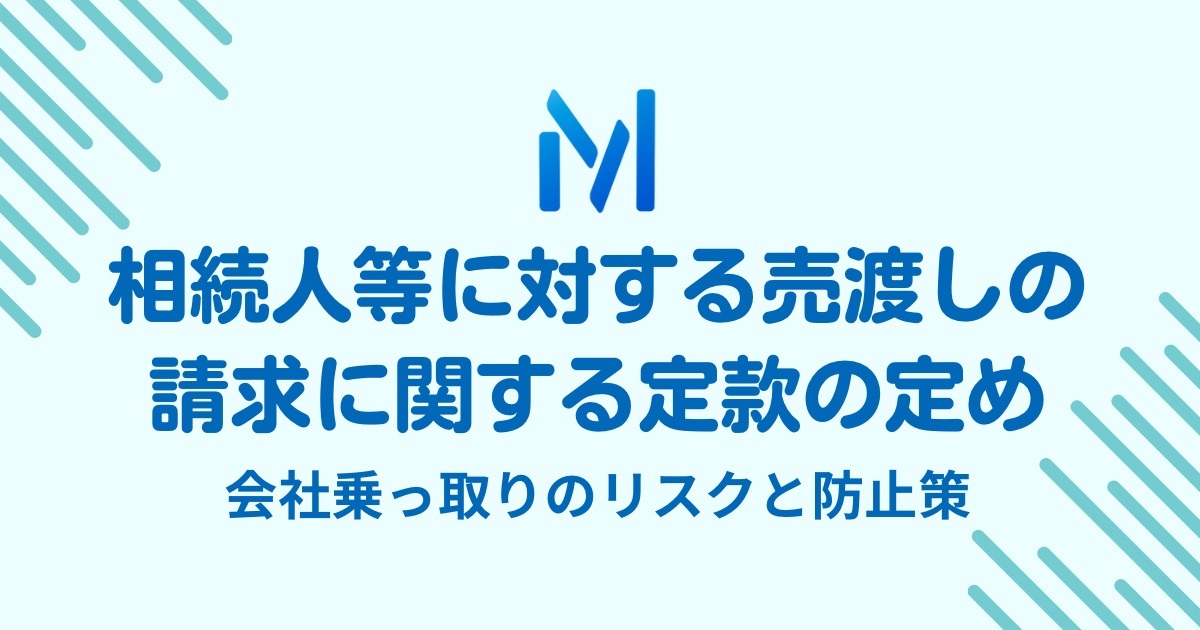
※本記事は、掲載時点で施行されている会社法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
※本記事で紹介するスキームは、その実行を推奨するものではありません。制度の悪用によるリスクを理解し、適切な防止策を講じるための情報提供を目的としています。
はじめに
相続人等に対する売渡請求制度(会社法174条)は、相続などで株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求できる制度です。株主構成の維持や事業承継の円滑化に有効ですが、議決権制限を利用した経営権奪取など悪用の懸念もあります。さらに、実行には分配可能額(会社法461条)の制約があり、思惑どおりに進まない場合もあります。本記事では、この制度の仕組み、悪用リスク、財務的制約、防止策を整理します。
法律上認められた定款規定
株式の譲渡制限に関する規定
会社法107条1項は、株式会社が株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定款で定められるとしています。これが譲渡制限株式です。譲渡制限は生前の譲渡(特定承継)にのみ直接効力を持ち、相続や合併等の一般承継には及びません。
<定款記載例(株式の譲渡制限に関する規定)>
第〇条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
相続人等に対する売渡しの請求(会社法174条)
この一般承継による株主変動を防ぐため、会社法174条は次のように規定しています。
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
<定款記載例(相続人等に対する売渡しの請求)>
第〇条 当会社は、相続その他一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求できる。
特別決議と議決権制限(会社法175条)
売渡請求を行うには、株主総会の特別決議で取得に関する一定の事項を定めなければなりません(175条)。
相続人等は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、相続人等以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない(175条2項)。
つまり、売渡請求の対象とされた相続人等は、この決議に参加できません。残る株主のみで特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)を通せる環境が生まれます。
悪用リスク:会社乗っ取りスキームとその対策
制度は事業承継保護が本来目的ですが、議決権制限を利用すれば経営権を奪うスキームに悪用され得ます。
典型的な流れ
- 事前仕込み:乗っ取りを狙う者が少数株主となり、定款規定がない場合は売渡請求条項を設定(175条2項但し書きの排除)。
- 相続発生:大株主が死亡し、その相続人が株式を取得。
- 議決権制限発動:相続人は売渡請求決議で議決権を行使できず、残りの株主だけで決議可能。
- 株式取得:会社が相続人から株式を取得し、残る株主が経営権を握る。
実務的制約:分配可能額の壁と守りの定款規定
会社法461条1項5号は、相続人等に対する売渡しの請求に際して交付する金銭等の帳簿価格の総額は、「分配可能額」を超えてはならないと定めています。
評価額が高く分配可能額を超える場合、合法的に取得できず、スキームは資金面で頓挫します(中小企業はほぼこれにあたると言われています)。
そのため過度に心配する必要はありませんが、念のため定款に「一定以上の株式が承継された場合は、この限りでない。」と定めることも対策の一つだと金子登志雄氏は提唱されています。
まとめ
相続人等に対する売渡請求制度は、非公開会社の株主構成を維持し事業承継を安定させる有力な制度ですが、定款の一文が経営権を巡る争いに悪用される危険もあります。また、分配可能額の制限が実行可否を左右します。
定款作成や変更の段階で、この制度を導入するか否かは慎重に判断すべきです。会社法に精通した弁護士や司法書士と相談し、自社の株主構成・財務状況・事業承継方針に照らして最適な設計を行うことが、将来のトラブル防止につながります。
参考文献
金子登志雄『事例で学ぶ会社法実務〈全訂第2版〉』中央経済グループパブリッシング、2023年
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。