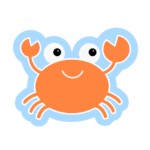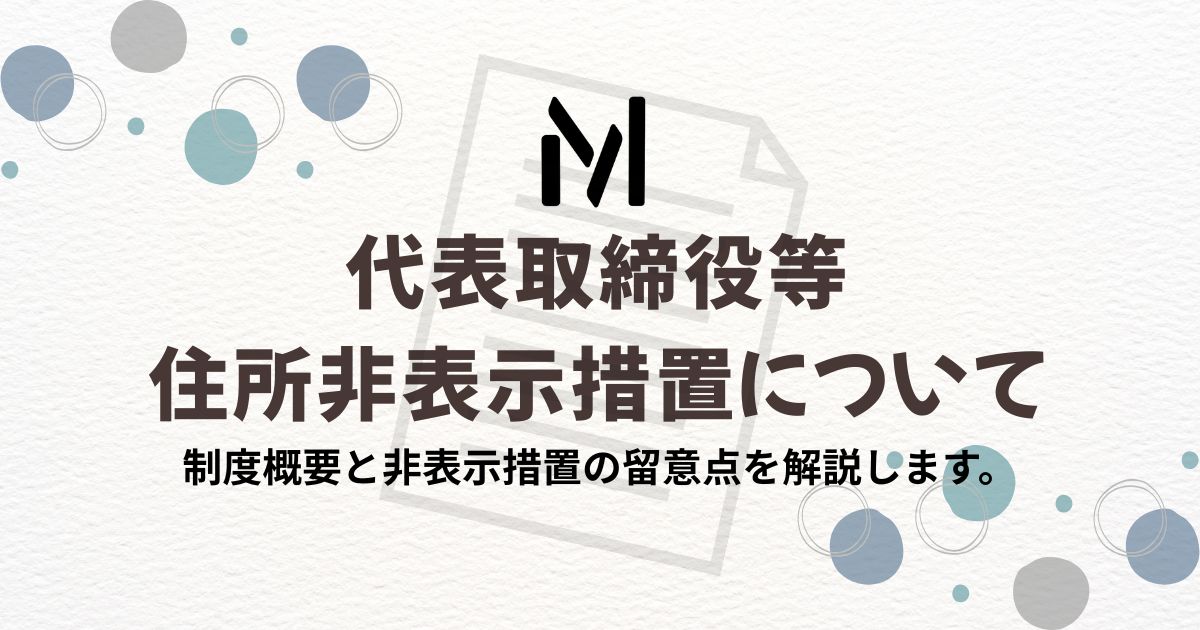相続登記の直後にDMが届くのはなぜか。行政開示の大原則と受付帳の見直しについて
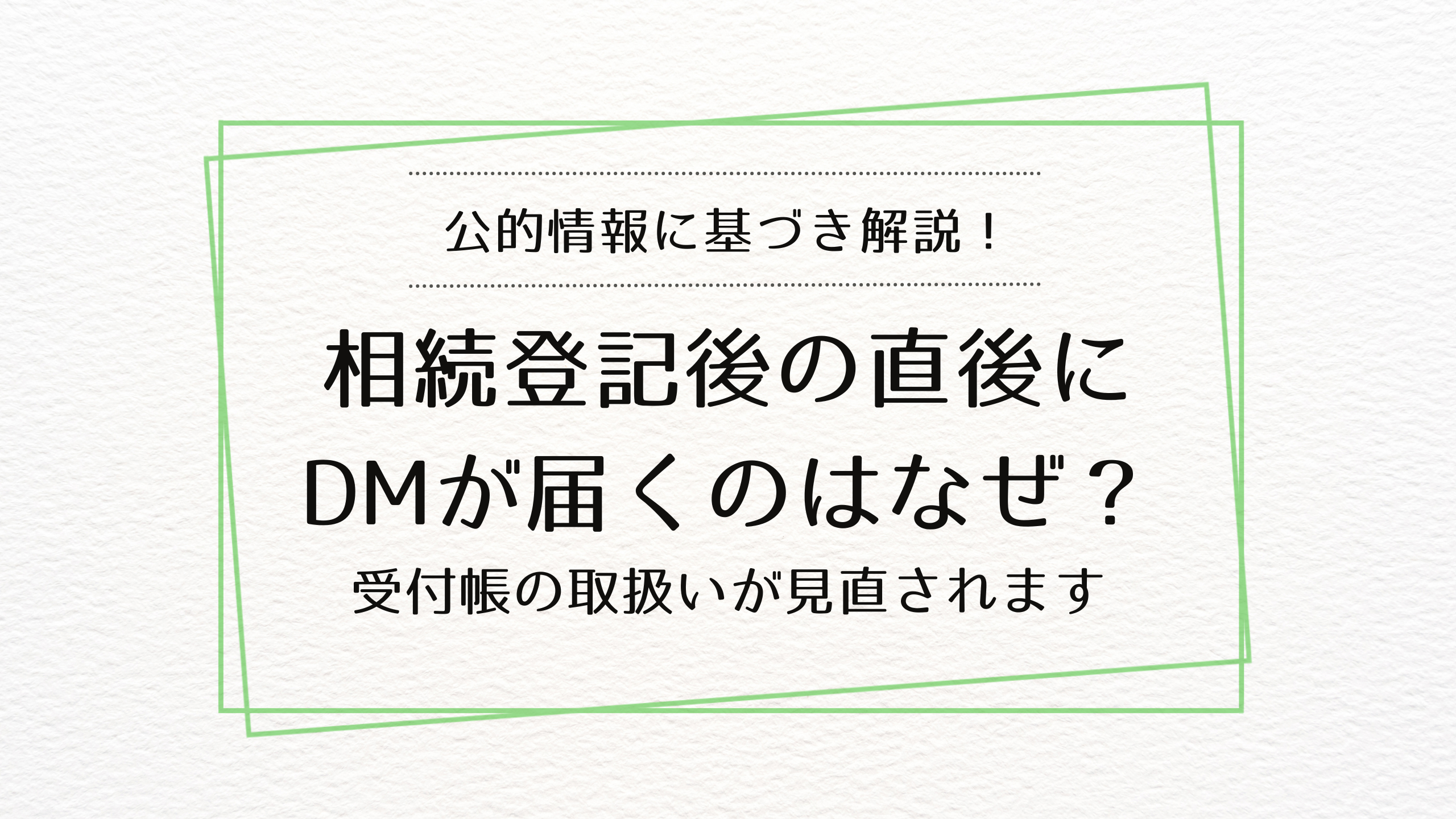
※本記事は、掲載時点で施行されている不動産登記規則その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに(背景)
相続登記の直後に不動産会社などから大量のダイレクトメール(DM)が届くことが問題視されています。
依頼者からは「登記直後にDMが殺到して不快だ」との声が上がり、司法書士実務にも疑問が投げかけられてきました。
本稿では、まず行政開示の大原則を確認し、その上でDMが届くメカニズムと受付帳見直し(省令案)の位置づけを整理します。
行政開示の大原則
行政機関が保有する行政文書は、原則として「何人も」開示請求できます(情報公開法3条)。
同法は、行政情報の公開を通じて国民の知る権利の保障、行政運営への理解と信頼の確保、民主主義の健全な発達に資することを目的とします(同法1条)。
また、「行政文書」とは行政機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有する文書等をいいます(同法2条2項)。
なぜ相続登記直後にDMが届くのか(情報の連鎖)
- 受付帳の開示請求:法務局が保有する受付帳は行政文書として扱われ、開示の対象となり得ます(情報公開法3条)。
- 対象不動産の特定:受付帳の記録等から、相続登記がなされた物件を把握できる場合があります。
- 登記事項証明書の取得:登記事項証明書は「何人も」手数料を納付して交付を請求できます(不動産登記法119条1項)。
- 氏名・住所等を基にDM送付:取得情報を基に、事業者がDMを送付する流れです。
受付帳見直し(省令案)の位置づけ
法務省は「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」を公表し、受付帳の記録事項から「登記の目的」及び「不動産所在事項」等を削除する方針(案)を示しています。
趣旨は、登記事務が全面デジタル化され、当該項目が事務処理上不要となったため、様式の見直しにより業務の適正化・効率化を図ることです。
施行期日(案)は令和8年10月1日です。
東京司法書士会の見解
東京司法書士会は当該省令案に賛成の立場を表明し、
- プライバシー保護の強化
- 登記事務処理期間の短縮への期待
- システム障害リスク低減の効果
を挙げています。
まとめ
- 行政開示の大原則(情報公開法3条)と、登記事項証明書の公開(不動産登記法119条1項)により、受付帳→登記事項証明書→DMという情報の連鎖が成立してきました。
- 省令案では受付帳の記録事項が削減され、令和8年10月1日施行(案)。結果として、相続直後のDM問題の緩和に加え、司法書士会が指摘するように、登記事務の効率化やシステム安定性向上といった副次的効果も期待されています。
参考文献
東京司法書士会「【会長声明】受付帳情報の開示に関する意見について」
https://www.tokyokai.jp/news/2025/07/post-602.html
法務省民事局「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」(令和7年7月公表、PDF資料)
「記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。」