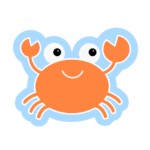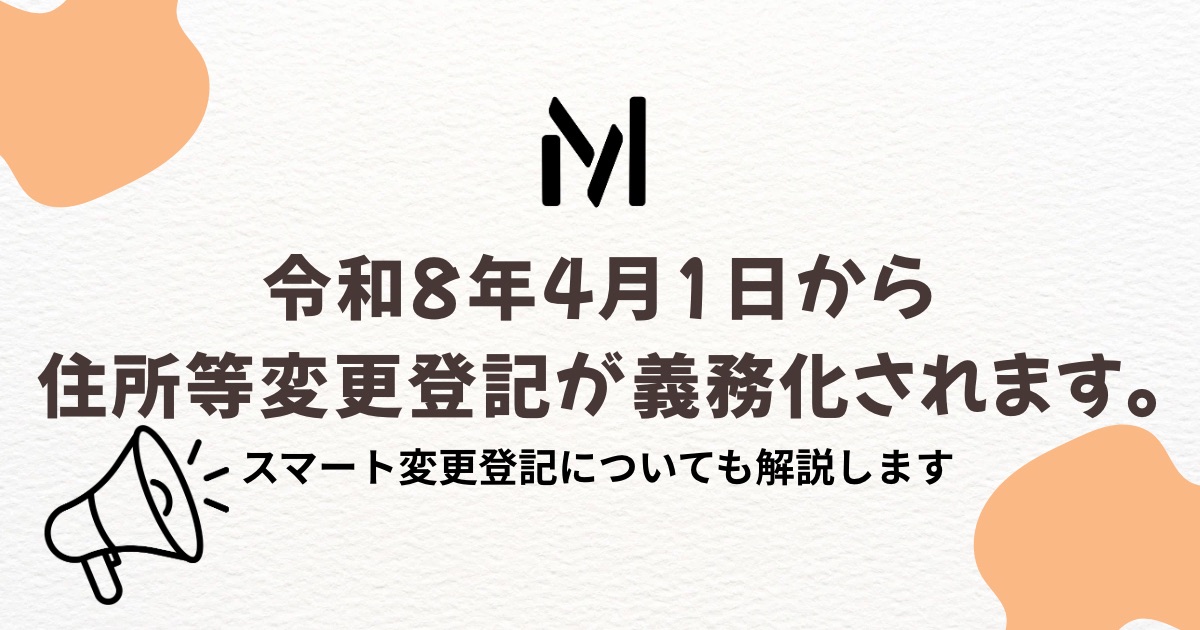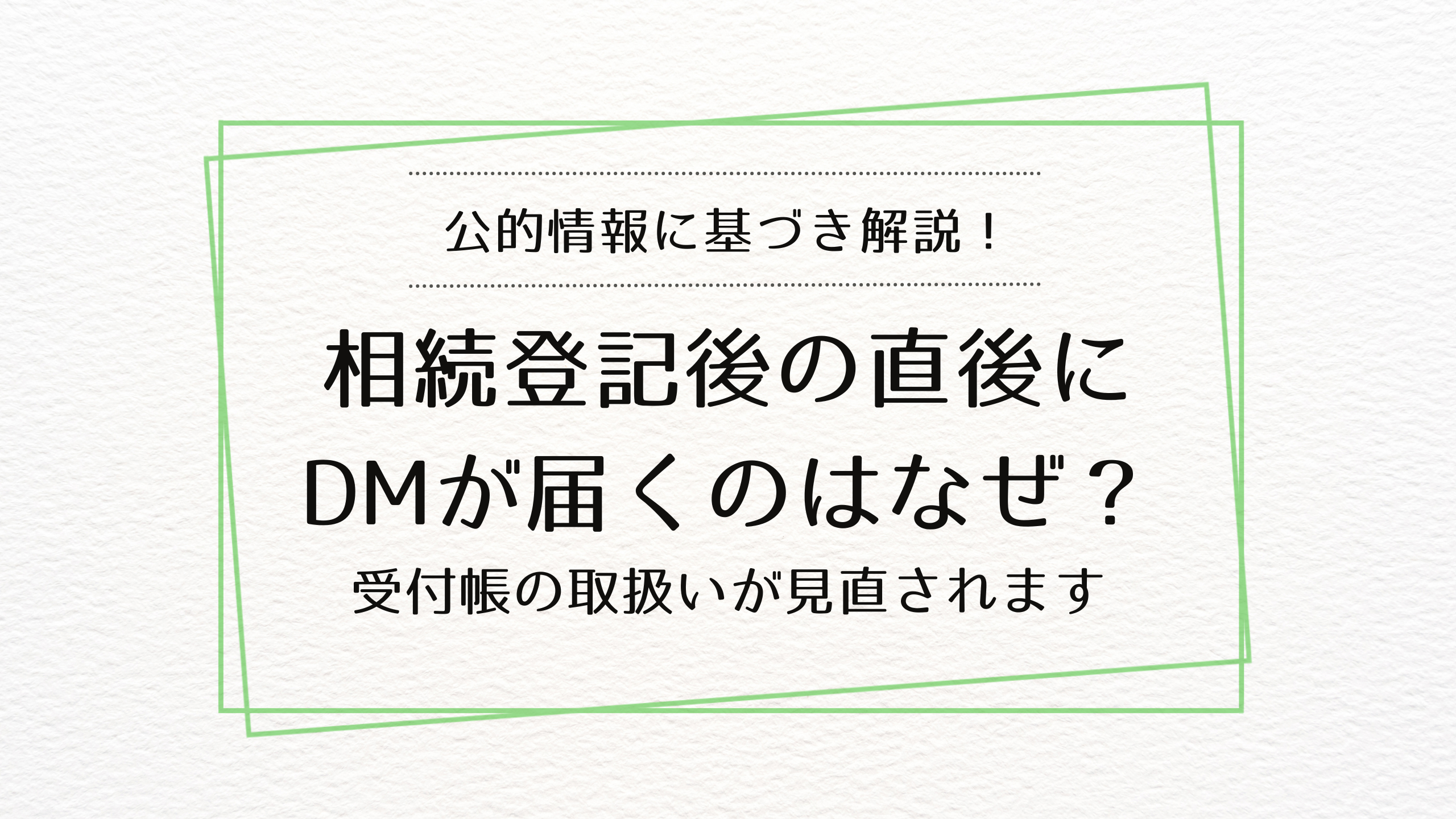相続手続を効率化する法定相続情報一覧図と相続関係説明図の基本と違いを解説します。

※本記事は、掲載時点で施行されている不動産登記法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
制度導入の背景
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の現在戸籍を集めなければなりません。転籍や改製で通数が増えると、銀行や証券会社、不動産登記など複数の手続先に同じ原本を出す必要があり、利用者にとって大きな負担でした。
この問題を解消するため、
- 各種手続で戸籍の束に代わる法定相続情報証明制度
- 登記手続を効率化する相続関係説明図
- 2024年からは法定相続情報番号による登記申請の添付省略制度も始まっています(不動産登記法76条の2)。
それぞれの制度をみていきましょう。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報一覧図とは、相続人が法務局に申請して交付を受ける「法定相続情報証明制度」に基づく書類で、被相続人の戸籍等を基に作成された相続関係を一覧化した図面です。戸籍謄本等の束を提出する代わりに利用でき、金融機関の手続や不動産登記申請において利便性が高い制度です。
- 認証文付き・偽造防止用紙で交付
- 必要であれば何部でも無料で請求可能
ポイント:登記官の確認・認証が入るため、金融機関で広く受け入れられる「公的な一覧図」です。
⚠︎注意事項
法定相続情報一覧図は、戸籍や除籍謄本の記載をもとに「法律上の相続人」を一覧化したものであり、相続放棄や遺産分割の結果とは関係なく、法定相続人に該当するすべての人が記載されます。したがって、最終的に遺産を取得しない人であっても一覧図には氏名等が含まれます。
つまり、相続放棄や遺産分割の結果は、別途証明しなければならないということです。
作成と交付の流れ
- 必要書類の収集:被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人全員の現在戸籍、住民票等を準備
- 一覧図作成:戸籍に基づき、相続人関係を図式化した「法定相続情報一覧図」を作成
- 申出:一覧図と戸籍一式を添付して次のいずれかの登記所に申出
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
登記官が確認し、認証文付き一覧図の写しが無料で交付されます。
最新情報:法定相続情報番号
2024年4月からは、交付された一覧図に記載の法定相続情報番号を登記申請書に記載するだけで、一覧図の写しや戸籍の添付を省略できます。
- 対象は法務局で行う不動産登記の申請等手続きに限られます。
- 保管から5年以上経過した一覧図など、番号を使えないケースがあるため注意が必要です。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人との続柄を図式化したもので、不動産の相続登記を申請する際に添付できる任意の書面です。戸籍謄本等の代わりに提出できるため、登記官に相続関係を分かりやすく示す役割を果たします。
- 相続登記に添付することで、戸籍原本を登記完了後に返却(原本還付)してもらえます。
- 書式は自由ですが、戸籍の記載と完全に一致していることが求められます。
ポイント:相続関係説明図自体に法務局の認証はなく、あくまで登記の補助的、説明資料です。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
- 法定相続情報一覧図:登記官の確認を経て交付される公的な一覧図。銀行や証券、相続税や年金など幅広い手続で利用可能。
- 相続関係説明図:登記の原本還付を受けるための説明資料。記載事項に規定はないため、相続放棄や遺産分割の結果なども記載可能。
まとめ
法定相続情報一覧図は、登記官の認証が入るため、銀行や保険会社など多くの相続手続にそのまま利用できる公的な一覧図です。相続関係説明図は、相続登記で戸籍原本を返却してもらうための便利な資料です。さらに2024年からは法定相続情報番号により、相続登記の添付書類を省略できる制度も導入されています。
状況に応じてこれらを使い分けることで、相続手続を効率的かつ円滑に進めることができます。
司法書士や弁護士等も依頼者の代理人としてこれらの書面を作成することができますので、必要に応じて専門家にご相談ください。
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。