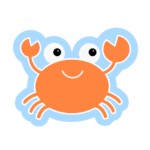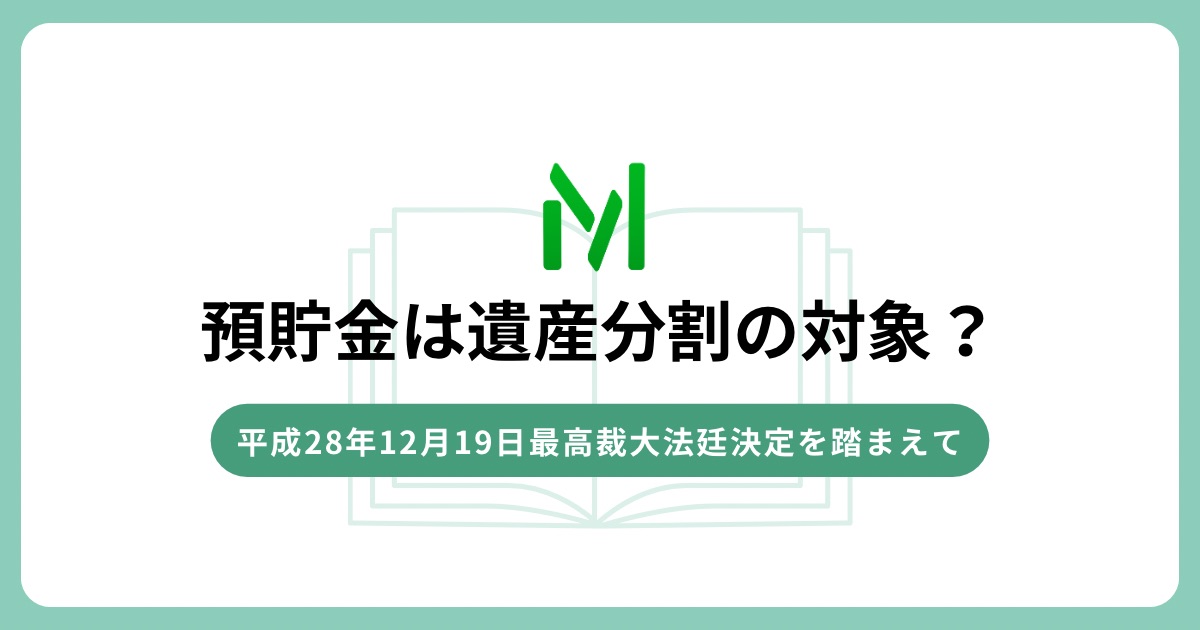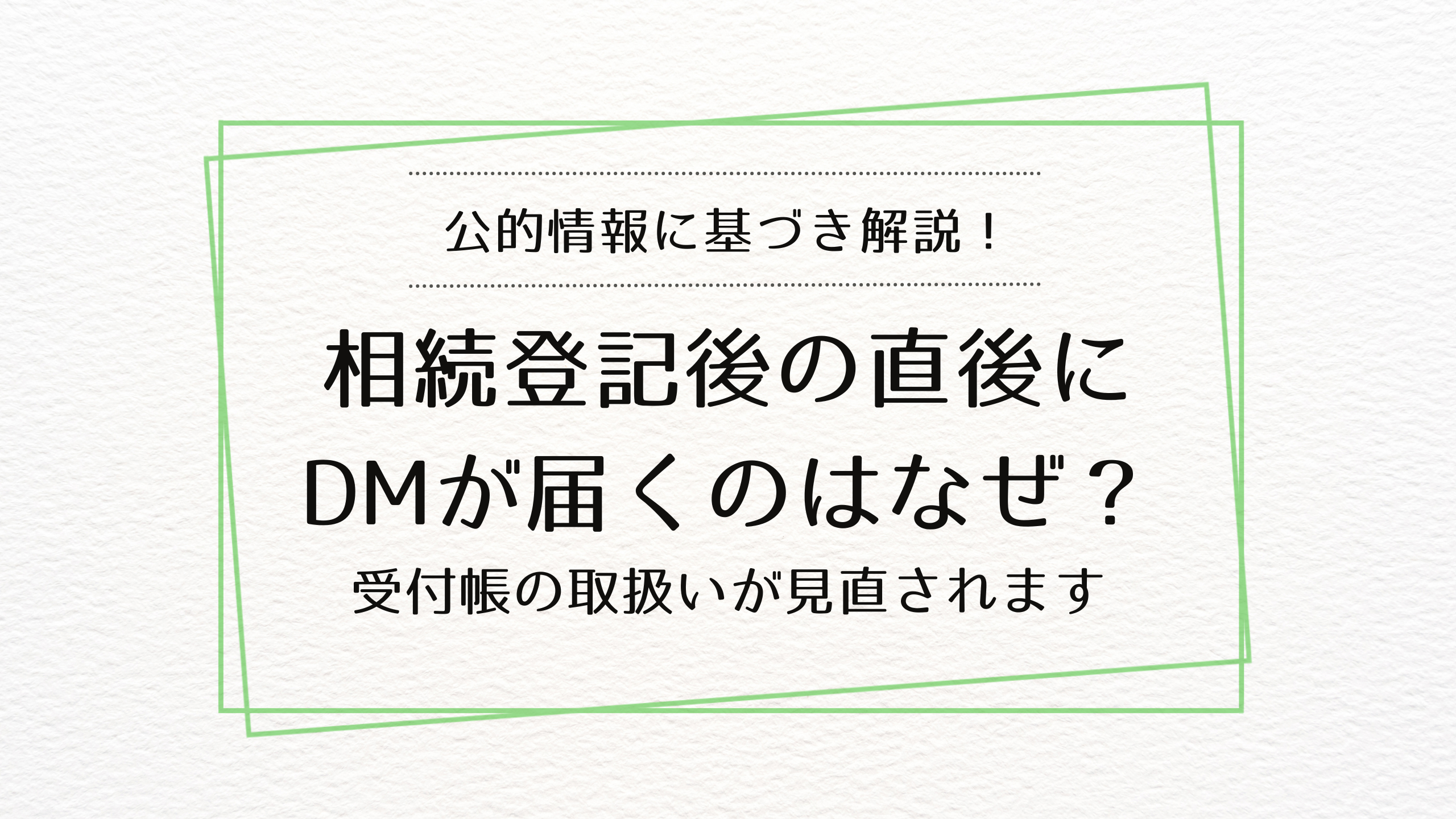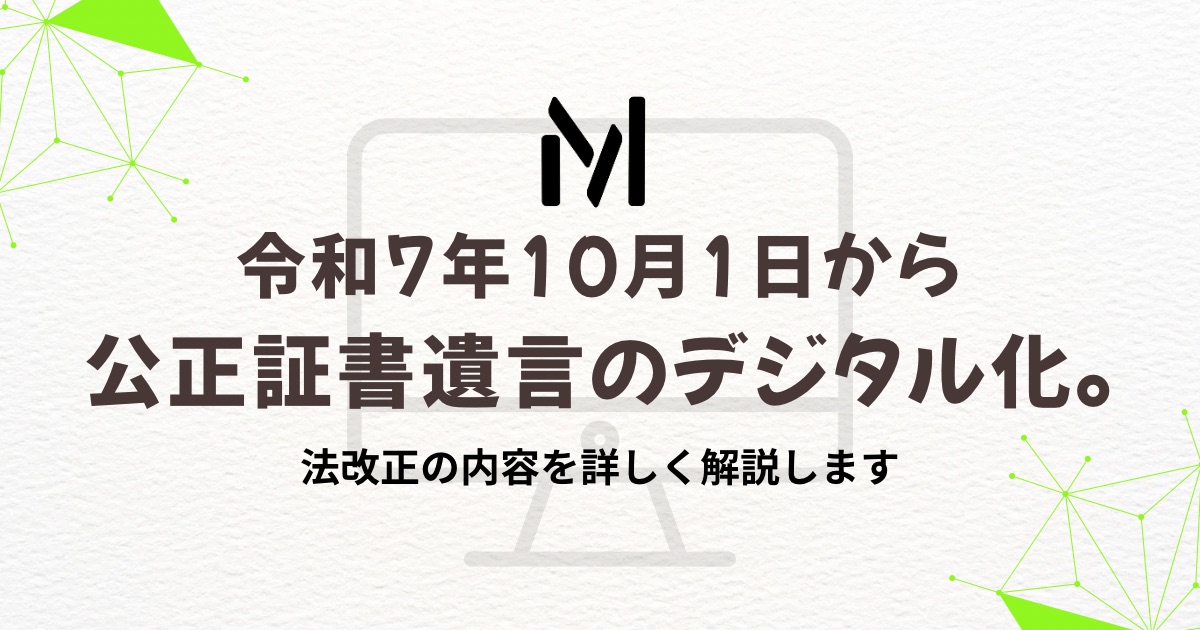普通方式遺言の3種類と要件・判例を解説【自筆証書・公正証書・秘密証書】

※本記事は、掲載時点で施行されている民法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに
遺言は、自分の死後の財産分配や意思を形にする重要な手段です。
民法は、通常時の遺言方式として「普通の方式遺言」を定め、これを自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3類型に分類しています。
これらは要件が厳格であり、一つでも欠けると無効になる可能性があります。
それぞれの要件や判例を見ていきましょう。
自筆証書遺言(民法968条)
要件
自筆証書遺言を有効に作成するためには、遺言者がその全文、日付および氏名を自ら手書きし、これに押印しなければなりません。
遺言に財産目録を添付する場合には、その目録については自書する必要はありませんが、各ページごとに遺言者が署名し、押印することが求められます。
さらに、遺言の加除訂正を行う場合には、訂正箇所を明示し、訂正の旨を付記したうえで特に署名押印をしなければ、その訂正は効力を生じません。
メリット
・自筆証書遺言は、公証人や証人が不要であり、費用をかけずに即日作成できることが大きな利点です。
・紙と筆記具さえあれば自宅で作成できるため、思い立った時にすぐに書くことができます。
・作成段階では内容を他人に知られずに済むため、生前の秘密保持にも適しています。
デメリット
・方式の一部でも欠けると無効になる可能性が高いことが大きな欠点です。
・日付の記載や押印の不備、他人による代筆などがあると、無効と判断される場合があります。
・遺言書を自宅等で保管する場合、紛失や偽造、相続人による隠匿の危険があります。
・自筆証書遺言は遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
主要判例
1. 添え手補助による自書(最判 昭和62年10月8日)
争点:遺言者が他人の添え手による補助を受けて遺言を書いた場合、民法968条1項の「自書」要件を満たすか。
判決:遺言者に自書能力があり、補助が筆記を容易にするための位置誘導等にとどまり、筆跡が遺言者自身のものである場合は有効としました。
2. 日付を「吉日」と記載(最判 昭和54年5月31日)
争点:日付欄に「昭和四拾壱年七月吉日」とのみ記載された遺言の効力。
判決:「吉日」は特定の日を明示せず、日付の要件を欠くとして遺言は無効としました。
3. 花押は押印に該当せず(最判 平成28年6月3日)
争点:印章の代わりに花押を記載した場合、押印要件を満たすか。
判決:花押は押印に該当せず、方式を欠くとして遺言は無効としました。
公正証書遺言(民法969条)
要件
公正証書遺言を有効に作成するためには、まず証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる必要があります。
公証人はその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人が筆記内容の正確性を承認した後、各自が署名押印をします。遺言者が署名できない場合には、その理由を公証人が付記し、署名に代えることができます。
最後に、公証人が方式どおりに作成された旨を付記し、署名押印して完成します。
メリット
・公証人という法律の専門家が関与するため、方式の不備による無効リスクは極めて低いです。
・遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。
・家庭裁判所の検認手続きが不要で、相続手続きが迅速に進められます。
デメリット
・作成には公証人手数料が必要であり、遺言財産額に応じて費用が高額になる場合があります。
・証人二人の立会いが必要で、遺言内容を証人や公証人に開示しなければならないため、内容の秘匿性は低くなります。
・公証役場まで出向く必要があり、身体的負担がかかる場合もあります。なお、公証人出張制度もあります。
主要判例
1. 「口授」がない場合(最判 昭和51年1月16日)
争点:遺言者が公証人の質問に対し、言語による申述を行わず、単にうなずきや首振りで応答した場合、「口授」に当たるか。
判決:最高裁は、「民法969条2号にいう口授とは言語による申述を意味し、うなずき等による応答ではこれを満たさない」と判断し、公正証書遺言は無効とされました。
2. 証人として不適格な者が同席していた場合(最判 平成13年3月27日)
争点:公正証書遺言作成時に、本来証人となる資格のない者が同席していたとしても、その方式が有効か。
判決:最高裁は、「その証人が遺言の内容に影響を与えたり、遺言者の真意表示を妨げる等の特段の事情がなければ、公正証書遺言は有効である」と判断し、遺言を有効としました。
秘密証書遺言(民法970条)
要件
秘密証書遺言を有効に作成するためには、まず遺言者が遺言書本文に署名押印をし、その遺言書を封入して封をし、本文に押したものと同じ印章で封印します。
そのうえで、遺言者は公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、これが自分の遺言書であることと、その筆者の氏名および住所を申述します。
公証人は封紙に提出日および遺言者の申述を記載し、遺言者および証人とともに署名押印をします。
メリット
・遺言の内容を生前に他人に知られることなく作成できる点が大きな利点です。
・本文を必ずしも自書する必要がないため、代筆やパソコンによる作成も可能です。
デメリット
・方式が複雑で、要件を一つでも欠くと無効になるおそれが高いです。封印や申述などの手続きを正確に行う必要があります。なお、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、その遺言として効力を有します。
・自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認手続きが必要であり、保管方法によっては紛失や隠匿の危険があります。
主要判例
秘密証書遺言における「筆者」の認定(最判 平成14年9月24日)
争点:ワープロを用いて「秘密証書遺言」書類の表題および本文を入力し印字した者が、民法970条1項3号の「筆者」に該当するか。また、筆者が遺言者本人でない場合、その氏名・住所を申述しなかったことが方式違反となるか。
判決:最高裁は、ワープロにより表題および本文を入力・印字したFが「筆者」に該当すると判断。遺言者Dは公証人に対し筆者であるFの氏名・住所を申述しなかったため、民法970条1項3号所定の方式を欠き、秘密証書遺言は無効であるとしました。
遺言選択のポイント
遺言方式は重視するポイントによって選択が異なります。
安全性を重視するなら、公正証書遺言が最も確実です。公証人が方式を確認し原本を保管するため、無効や紛失のリスクが低く、検認も不要です。このため専門家は公正証書遺言を勧めることが多くあります。
費用や手軽さを優先するなら自筆証書遺言が適し、法務局の保管制度を利用すれば安全性も向上します。なお、法務局が保管しているからといって遺言の有効性が肯定させるわけではありません。
内容の秘匿を重視する場合は秘密証書遺言もありますが、方式が複雑で無効リスクが高く、特段の理由がない限り利用は少ないのが実情です。
まとめ
普通方式遺言は、方式の厳守が絶対条件です。
確かに判例で有効と認められた方式もありますが、その事案が最高裁まで争われたという事実自体が、大きなリスクを伴う選択であることを物語っています。
確実に意思を実現するためには、民法の条文に沿った遺言書を作ることが何よりも大切です。そのためにも、早い段階から専門家と相談しながら、万全の備えで自分の想いを未来に託していく。それが大切だと考えます。
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。