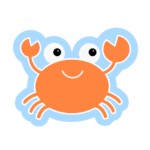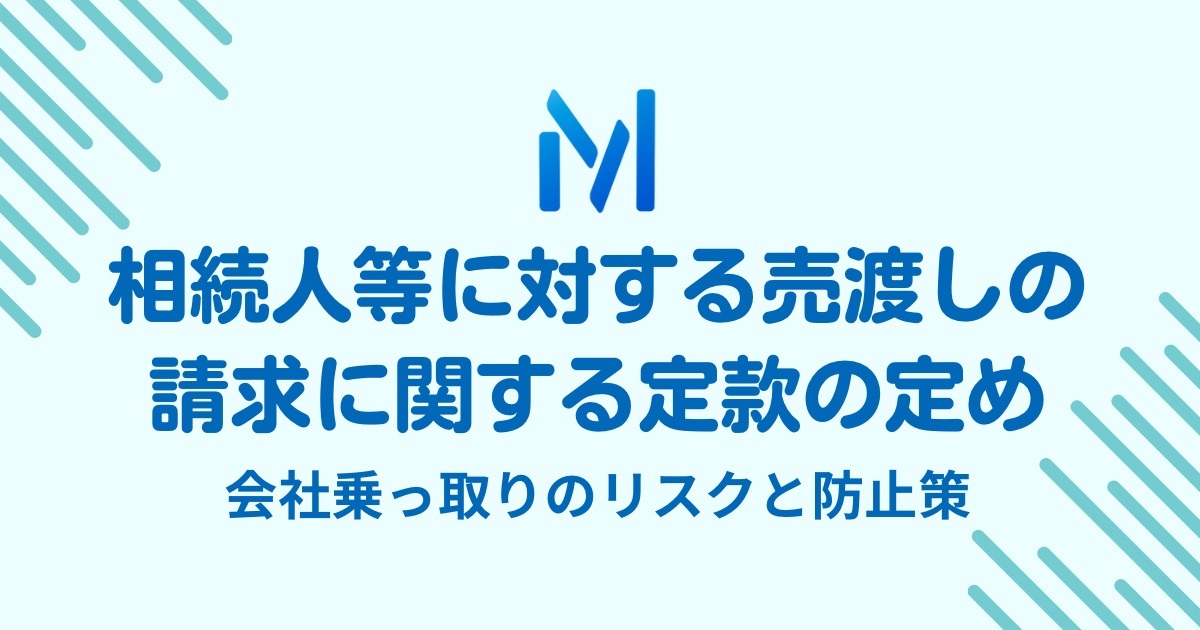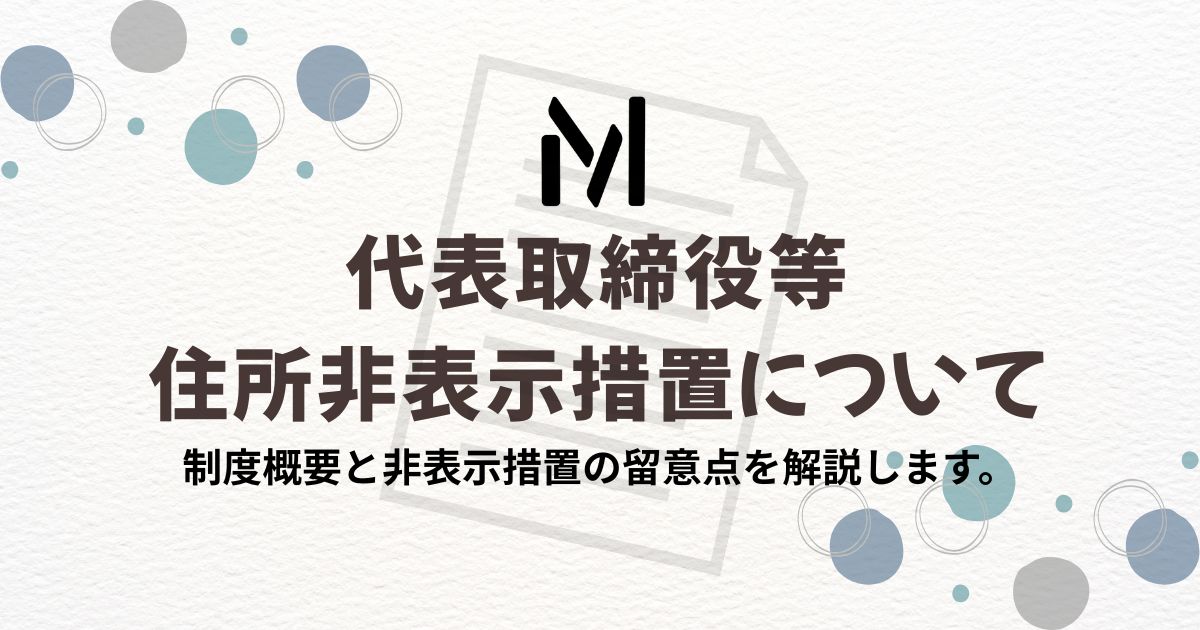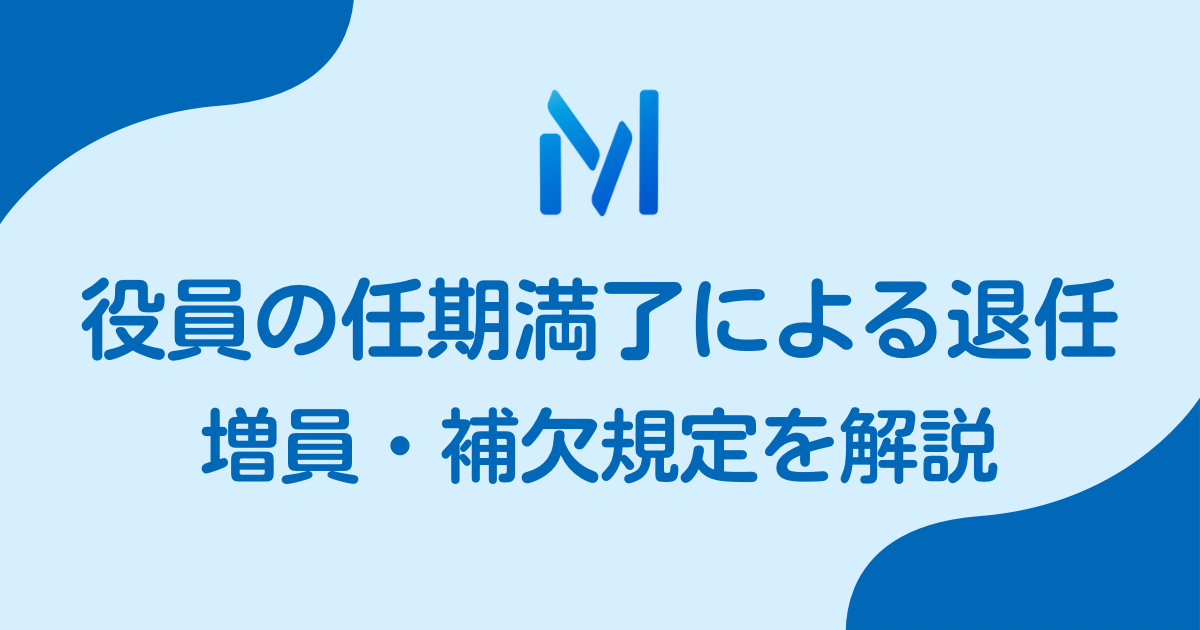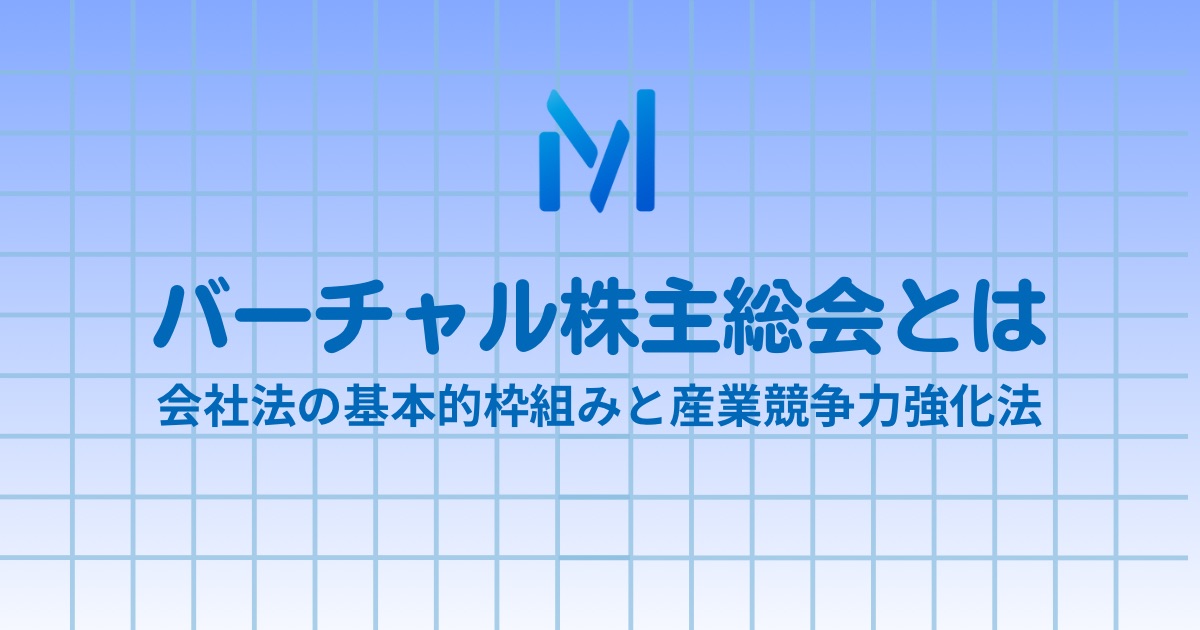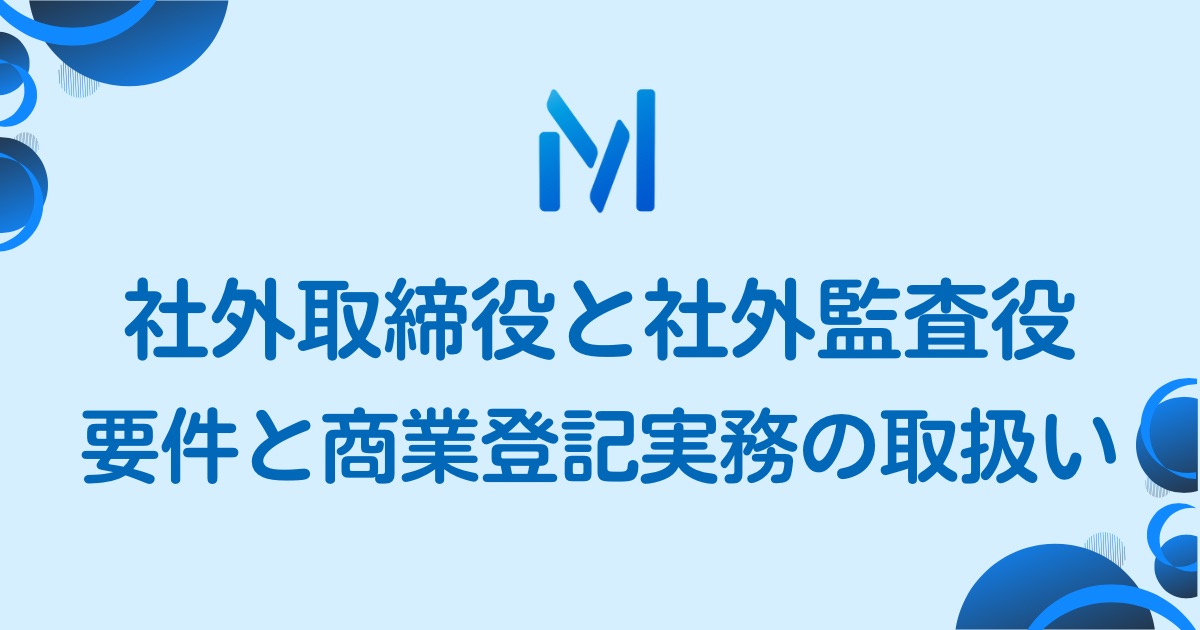自己の株式の取得ができる場合を整理|株主との合意による取得を中心に

※本記事は、掲載時点で施行されている会社法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに
自己株式の取得は、資本維持・株主平等の原則に密接に関わるため、会社法は155条以下で要件等を詳細に規定しています。本稿では、株主との合意による取得を中心に条文に沿ってその要件を整理します。
取得できる場合の限定列挙(会社法155条)
株式会社が自己株式を取得できるのは、同条各号に掲げる場合に限られます(限定列挙)。
会社法155条各号(要約版)
一 取得条項付株式の取得事由が生じた場合
二 譲渡制限株式の譲渡拒否による買取請求があった場合
三 株主との合意による取得決議があった場合
四 取得請求権株式の取得請求があった場合
五 全部取得条項の決議があった場合
六 相続人等に対する売渡請求をした場合
七 単元未満株主の買取請求があった場合
八 所在不明株主等の買取事項を定めた場合
九 1株未満の端数処理による事項を定めた場合
十 他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
※正確な表現は条文をご確認ください。
法務省令で定める場合とは、自己の株式を無償で取得する場合等が規定されています(会社法施行規則27条)。
株主との合意による取得
総則
株式の取得に関する事項の決定(会社法156条)
自己株式を株主と合意で有償取得するには、事前に株主総会決議(普通決議)で次の事項を定める必要があります。
- 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
- 株式を取得することができる期間
取得価格の決定(会社法157条)
取得の都度、次の事項を定める必要があります(取締役会設置会社にあっては取締役会による)。
- 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
- 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
取得の条件は各回ごと均等に取り扱う必要があります。
通知と申込み(会社法158条・159条)
157条で定めた事項は株主に通知し(公開会社は公告で代替可)、株主は申込株数を明示して申込みます。
会社は譲渡しの申込期日にその承諾をしたものとみなされます。
申込数が取得する自己の株式の数を上回った場合は、次のような計算になります。
自己の株式の取得総数:100株
申込総数:250株
内訳
A株主 100株
B株主 80株
C株主 70株
■計算
按分率=取得総数 ÷ 申込総数 = 100 ÷ 250 = 0.4
A株主:100 × 0.4 = 40株
B株主: 80 × 0.4 = 32株
C株主: 70 × 0.4 = 28株
(小数点以下は切り捨てます)
■結果
A株主から 40株
B株主から 32株
C株主から 28株
特定の株主からの取得(会社法160条〜164条)
特定株主を定める決議と売主追加請求(会社法160条)
特定の株主から取得する場合には、取得事項の決定(156条)と併せて、株主の通知(158条)を特定株主に対して行う旨を株主総会の決議(特別決議)で定められます。
会社は全株主に対して、特定の株主に自己をも加える旨を議案とすることを請求できる旨を通知する必要があります。
その旨を請求した株主は原則として当該株主総会で議決権を行使できません。
市場価格のある株式の取得の特則(会社法161条)
対象が市場価格のある株式で、1株当たり対価が法務省令の方法で算定される市場価格を超えないときは、売主追加請求に関する160条2・3項は適用されません。
相続人等からの取得の特則(会社法162条)
相続その他の一般承継により株式を取得した者からの取得について、手続の簡素化等の特則が置かれています。
子会社からの株式の取得(会社法163条)
子会社が保有する親会社株式を親会社が取得する場合、156条の「株主総会」は「株主総会(取締役会設置会社は取締役会)」と読み替え、157〜160条は適用されません。
定款による売主追加請求の排除(会社法164条)
定款で160条2・3項を適用しない旨を定められます。
〈定款記載例〉
(自己の株式の取得)
第○条 当会社は、株主総会の決議により、特定の株主との合意によりその有する株式の全部又は一部を取得することができる。
2 前項の場合、当該特定の株主以外の株主は、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができない。
ただし、株式の発行後に新たに定める・変更する場合(廃止を除く)は、当該株主の全員の同意が必要です。
市場取引等による取得(会社法165条)
市場内取引や金商法に規定する公開買付け(TOB)等による自己株式取得については、157〜160条は適用されません。
財源規制:分配可能額の制限(会社法461条)
自己株式の取得等に係る対価の帳簿価額の総額は、効力発生日における分配可能額を超えてはなりません。
なお、単元未満株主の買取請求は、分解可能額の制限はありません。単元未満株主の保護を会社法は重要視しているからです。
関連:自己株式の消却(会社法178条)
会社は取得した自己株式を消却できます。消却に際しては、取締役の過半数の決定(取締役会設置会社では取締役会決議)で消却する自己株式の数(種類株式発行会社は種類及び種類ごとの数)を定めなければいけません。
自己株式の消却は、発行済株式の総数に変更が生じるため、効力発生から2週間以内に変更登記をする必要があります。
おまけ:『自己の株式』と『自己株式』の違い
- 自己の株式
会社が保有していない自社株を指す定義語です。「会社法第4節 自己の株式の取得」などで使われています。
- 自己株式
会社が既に保有している自社株を指す定義語です。「会社法178条 株式会社は自己株式を消却することができる」などで使われています。
自己株式の取得は、既に保有している株式を取得するという意味になってしまうため、会社法に詳しい人からすると気になってしまうかもしれません。
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。