記事内に商品プロモーションを含む場合があります
※本記事は、掲載時点で施行されている民法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに
親と未成年の子が相続人に含まれるとき、遺産分割の有効性が後日争点となることがあります。
どこで利益相反が生じやすいのか、判例が採る判断枠組みは何か、また“協議をしない相続登記”はどう取り扱うのかを、実務で迷いやすい論点に絞って整理します。
判例:客観的性質で捉える利益相反基準
1.最判昭49年7月22日(利益相反行為の意義)
この判例は、利益相反行為の判断基準を明確にした重要なものです。
- 利益相反行為の意義
民法826条2項にいう「利益相反行為」とは、行為の客観的性質上、数人の子ども同士に利害の対立が生じるおそれがある行為をいいます。
実際にその結果として利害が対立したかどうかは問われません。
- 遺産分割協議の位置づけ
遺産分割協議はまさにこの「利益相反行為」に該当します。
たとえば、共同相続人の中に複数の未成年者がいて、彼らが相続権を持たない親権者に服している場合、その親権者に代理される一人を除き、他の未成年者についてはそれぞれ特別代理人を選任しなければなりません。
つまり、遺産分割協議は未成年者間に潜在的な利害対立を含むため、一律に利益相反行為と扱うのが最高裁の立場です。
2.最判昭和48年4月24日(数人の子を代理した協議の効力)
この判例は、親権者が子どもを代理して遺産分割協議をした場合の効力を判示しています。
- 親権者が相続人である場合
親権者が数人の未成年の子を代理して遺産分割の協議を行うとき、
たとえ親権者に「誰かを不利に扱おう」という意図がなく、また結果的に子ども同士に利害の対立が現実化していなかったとしても、
それはなお民法826条2項所定の利益相反行為に該当します。
- 協議の効力
このように親権者が代理して成立させた遺産分割協議は、追認がない限り無効とされました。
特別代理人の要否(パターン別)
パターン1:親と未成年の子が共同相続人
- 例:父が死亡し、母と未成年の子が相続人となる。
- 母は自分も相続人であるため、母が子を代理すると利益相反。
- 👉 子のため特別代理人が必要。
パターン2:未成年の兄弟姉妹が複数相続人で、親は相続人でない
- 例:父が死亡し、母(相続放棄)が親権者、相続人は未成年の子3人。
- 兄弟姉妹の取り分を決める遺産分割協議では、一方を代理すれば他方の取り分に影響。
- 👉 代理された1人の未成年者を除く各未成年者(2人)に特別代理人が必要。
パターン3:親が相続人でないが、未成年の子と成年の子が相続人
- 例:父が死亡し、母(相続放棄)が親権者、相続人は未成年の子と成年の子。成年の子は自己判断で協議参加、未成年の子は親権者が代理。
- 利害対立は「未成年の子」と「成年の子」の間で生じるが、親権者自身は相続人でないため親が代理すること自体は利益相反に当たらない。
- 👉 特別代理人は不要。
パターン4:遺産分割協議ではなく、法定相続分どおりに登記する場合
- 協議をせず、そのまま法定相続分で相続登記。
- 各相続人の持分は法律で規定されているため、協議そのものが存在しない。
- 👉 特別代理人は不要。
おまけ:親が未成年の子を代理して相続放棄の申述する場合
- 👉 特別代理人が必要。なお、親が子に先行して、もしくは、同時に相続放棄をする場合は不要。
よくある誤解
- 「公平に分割したから大丈夫」
利益相反の当否は結果ではなく行為の客観的性質で判断します。公平な結果でも、協議で取り分を定め直す限り利益相反に該当します。
- 「子の取り分を法定相続分より多くした。子に不利益ではないから大丈夫」
それでも利益相反です。有利・不利ではなく、遺産分割という行為の客観的性質で判断されます。
- 「親が相続人でなければ代理して大丈夫」
親が相続人でなくても、未成年の兄弟姉妹間で取り分を協議によって動かすなら、子同士の間で利益相反(双方代理)の構造が生じます。
まとめ
- 遺産分割協議の利益相反は客観的性質により判断されます。
- 一方、法定相続分どおりの相続登記のように協議を伴わない場面では、特別代理人は不要とされます。
参照判例
最判昭49年7月22日(利益相反行為の意義)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66769
最判昭和48年4月24日(数人の子を代理した協議の効力)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62128
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。
ABOUT ME
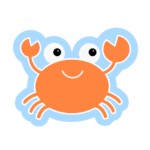
会社法・商業登記分野を中心に、司法書士の視点からわかりやすくお伝えしています。
