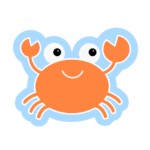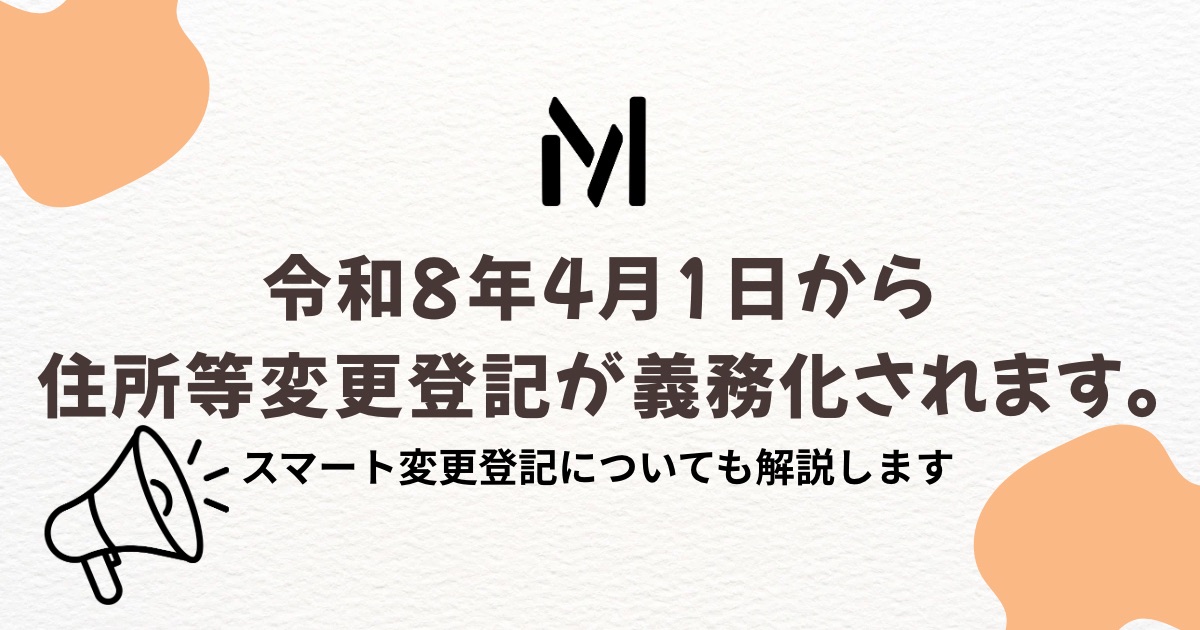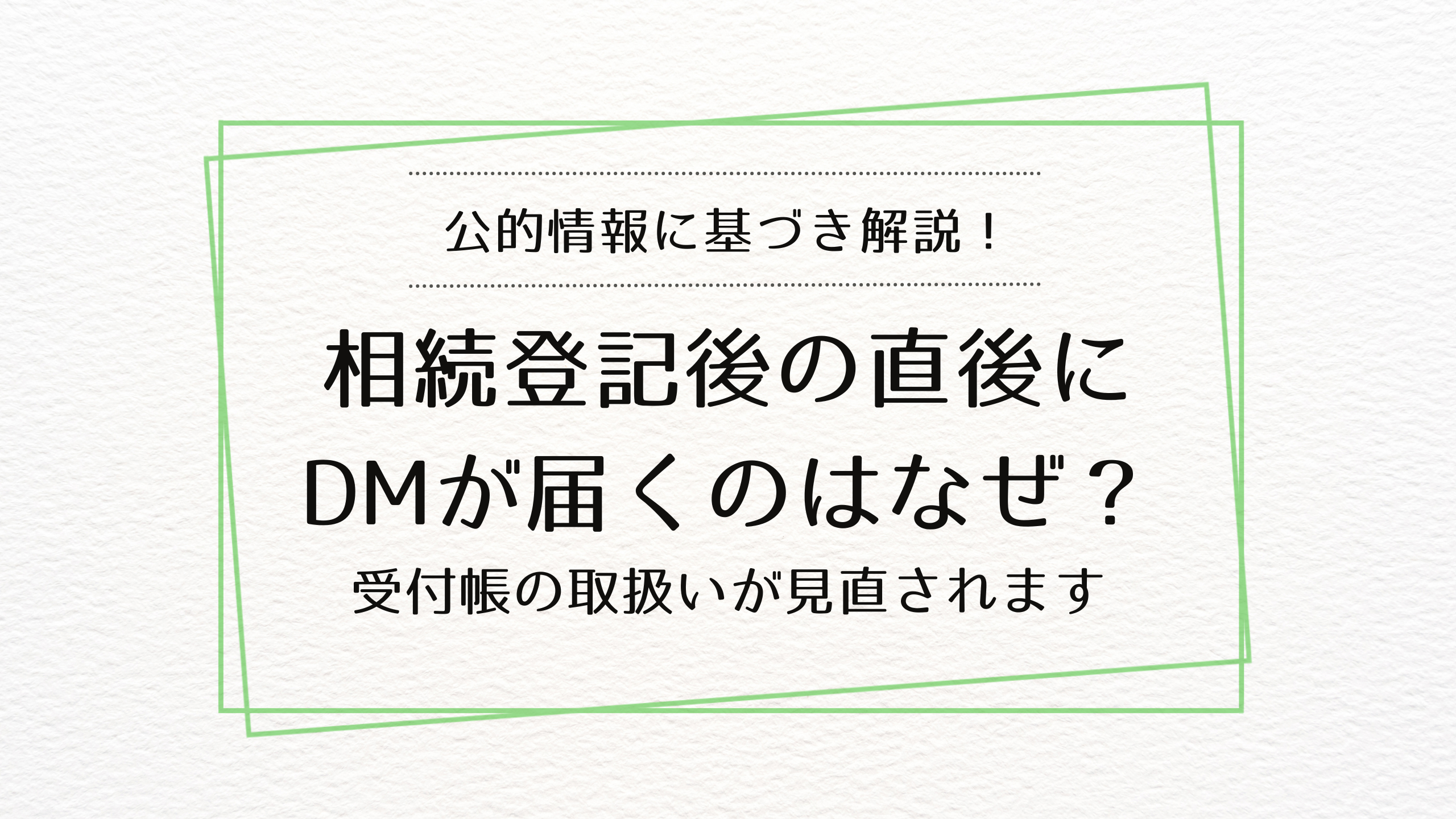「一人遺産分割協議」は登記できる?裁判例と通達で読み解く相続登記の可否と根拠を簡潔に解説!

※本記事は、掲載時点で施行されている民法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
はじめに(一人遺産分割の定義)
本記事において「一人遺産分割」とは、複数の相続人による遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、相続人の一部が死亡した結果、最終的に残った相続人一人だけで遺産分割が成立したかのように主張して登記を行おうとする場合を指すこととします。
東京地裁・東京高裁の判断により、法務省民事局は平成28年通知(法務省民二第154号)で一定の指針を示しており、それらを押さえることで、可/不可の線引きがクリアになります。
では、結論をさっそく見ていきましょう。
パターン別の結論
前提事例
被相続人Aが死亡。相続人はB及びC。
次いでBが死亡。相続人はCのみ。
パターンⅠ:遺産分割協議が未了のまま相続人Bが死亡し、最終的に相続人がCのみになった
- 結論:登記不可。
東京地裁平成26年3月13日判決・東京高裁平成26年9月30日判決は、一人となった相続人Cが亡Bの身分と併せて遺産分割したかのような主張に基づく登記(中間省略登記)は認められないと判示しました。 - 正しい登記手順:
①A→B・Cへの法定相続分による相続登記 → ②B死亡に伴うB持分全部移転登記(B→C) → 結果としてC単独名義、という二段階が必要です。 - 根拠:
登記研究758号及び同759号
登記原因証明情報(遺産分割協議書)の提供がない等
パターンⅡ:B生存中にB・C間で遺産分割協議が成立していたが、書面化前にBが死亡し、結果として証明者がC一人になった
- 結論:登記可能。
遺産分割は要式行為ではなく、口頭でも有効です。 - 法務省民二第154号は、C単独の遺産分割協議証明書+印鑑証明書でA→C登記が可能と整理しています。
(遺産の分割の効力)
民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。以下略
まとめ
裁判例によると、一人遺産分割は不可というのが結論になります。遺産分割は複数人ですることが想定されており、数次相続により一人の相続人に帰属した財産は遺産分割の余地がなく、実体法に根拠がない登記原因証明情報では登記申請が却下されるという考え方でしょう。
通達によると、遺産分割は要式行為ではないという理由から、第二相続が開始される前に複数人で遺産分割をしていた場合は、証明できる者が一人となっても有効に成立している事実は変わらず、登記申請も受理されるという取扱いです。
もっとも、不動産登記法61条により、登記原因証明情報としてその事実を証する書面の添付が求められます。
詳細は裁判例等をご確認ください。
参考文献
東京高等裁判所平成26年9月30日判決(平成26年(行コ)第116号処分取消等請求控訴事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf東京地方裁判所平成26年3月13日判決(平成25年(行ウ)第372号処分取消等請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf平成28年3月2日 法務省民二第154号
「遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について」
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。