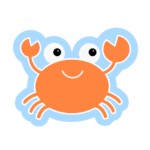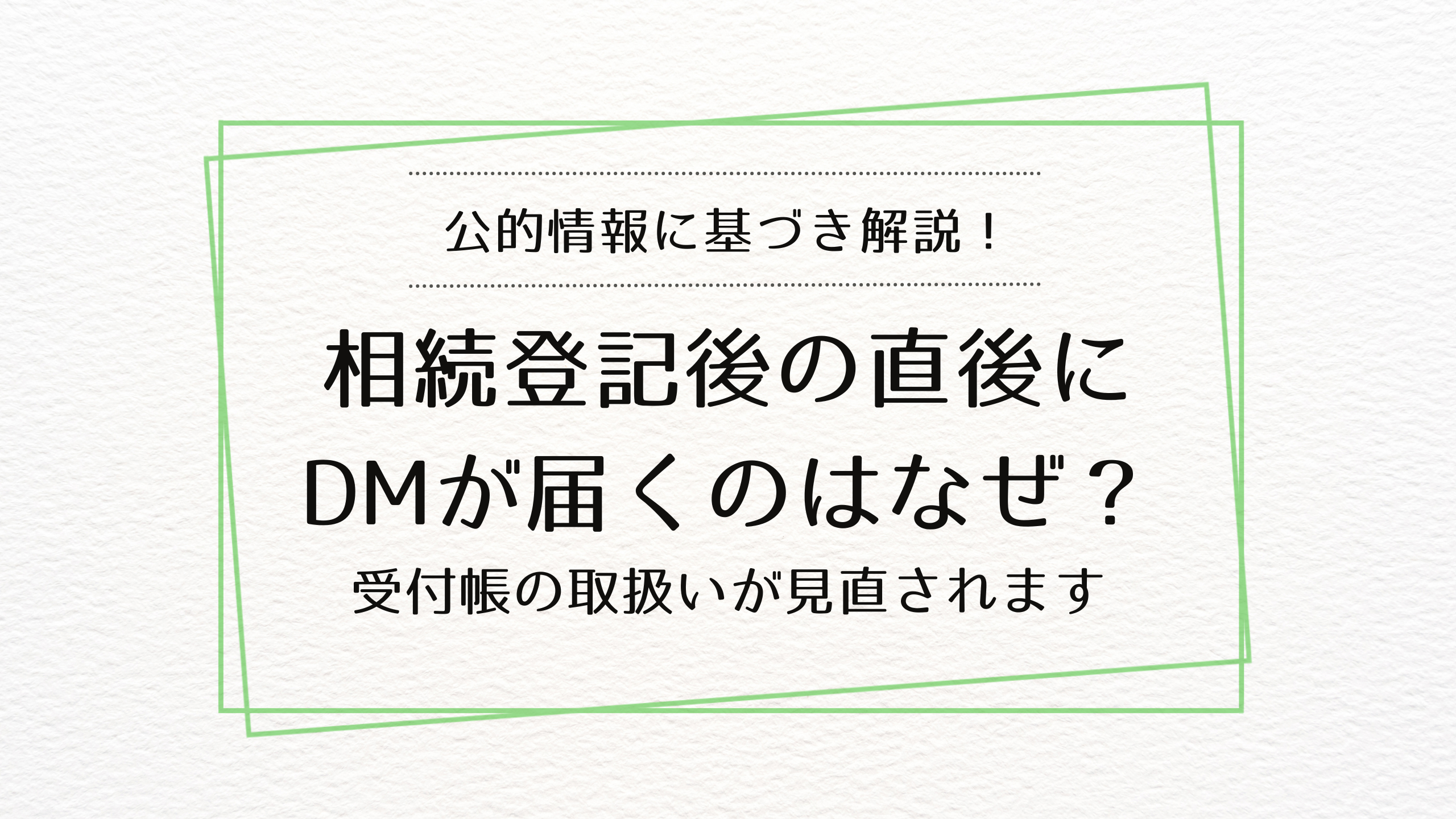【令和8年4月1日施行】住所・氏名変更登記の義務化を解説(スマート変更登記を活用しよう)
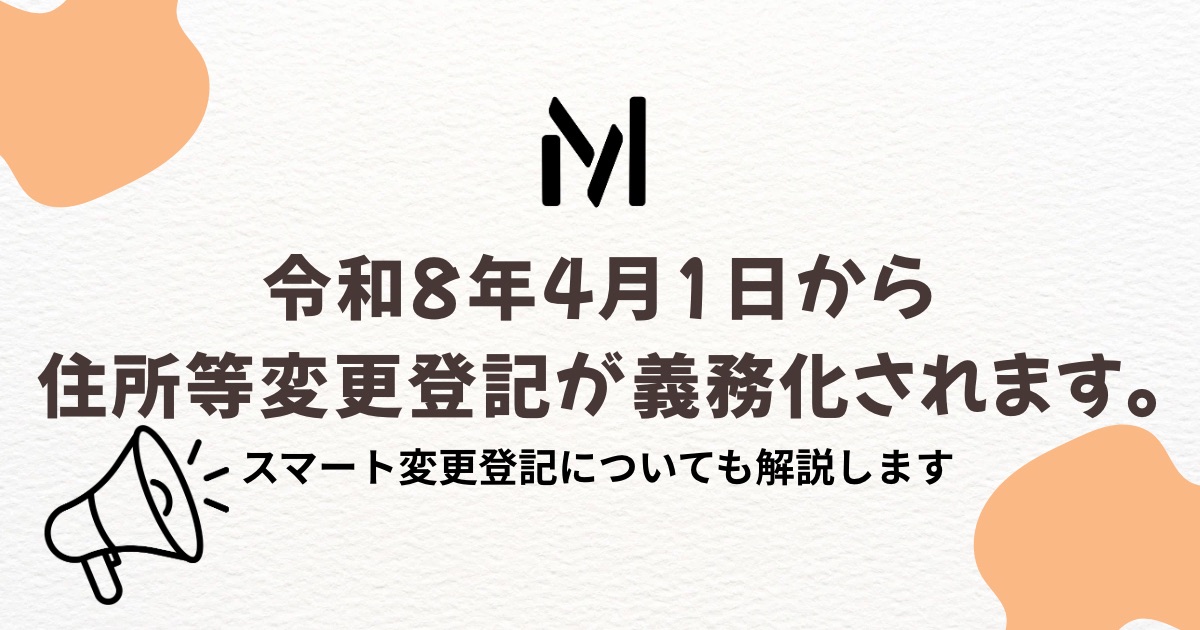
legal-toukilab_2025
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
※本記事は、掲載時点で施行されている関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
Contents
改正の背景
引っ越しや結婚などで住所や氏名(法人は商号や本店)が変わっても、登記簿の記載をそのままにしているケースは少なくありません。
これが積み重なると、相続や売買などの場面で所有者を特定できなくなる、いわゆる「所有者不明土地」の原因となります。
この問題に対応するため、不動産の所有者(所有権の登記名義人)に住所・氏名等の変更登記の申請義務が設けられました(不動産登記法76条の5)。
法改正の内容(対象・期限・罰則)
制度の要点をチェック
- 対象者:不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)
- 施行日:令和8年4月1日(施行日前に変更があったものも対象)
- 申請期限:変更日から2年以内
- 罰則:正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料
正当な理由とは、行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合や住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合などを指します。
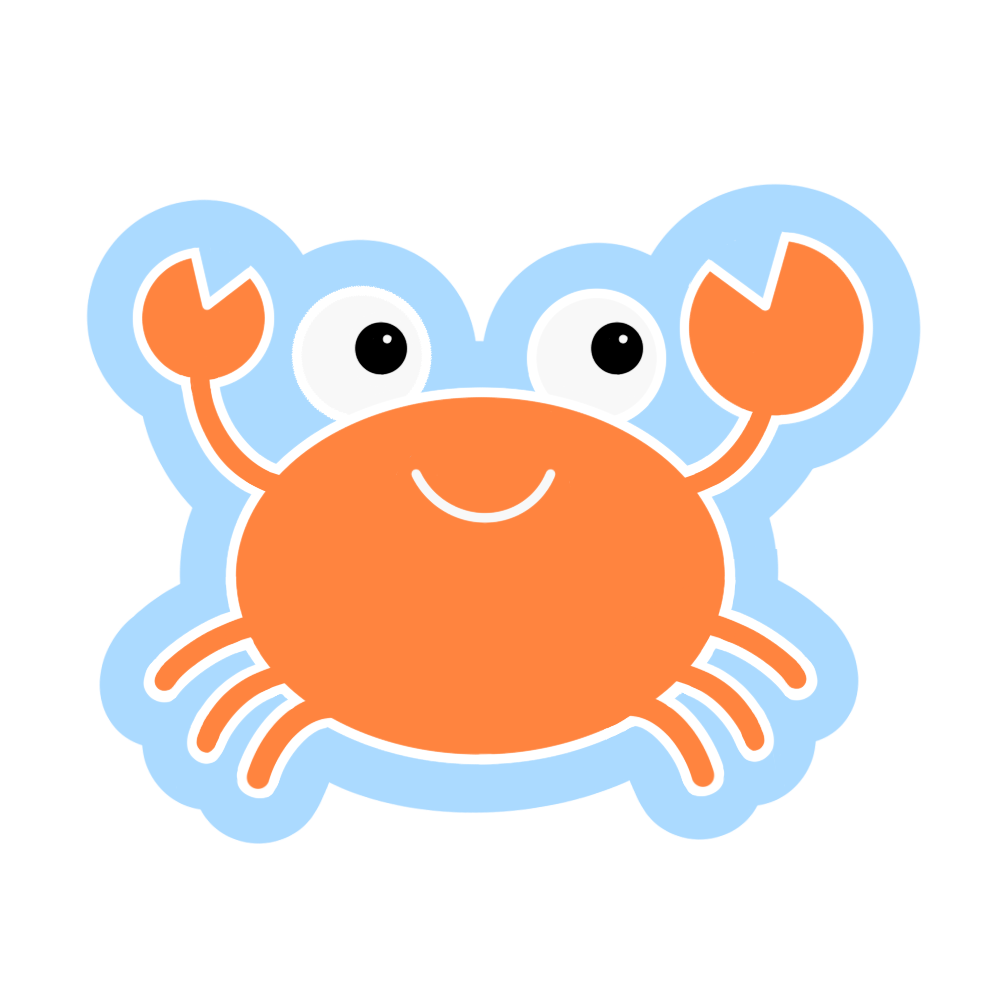
経過措置(施行日前の変更)
令和8年3月31日以前に住所や氏名が変わっていて、まだ登記をしていない場合も対象です。その場合の申請期限は令和10年3月31日までとされています。
手数料・登録免許税
- 通常の変更登記(申請型):不動産1個につき1,000円
- スマート変更登記(職権型):事前に「検索用情報の申出」をしておけば、登記官が職権で変更を反映し、登録免許税は不要(後述します)。
負担軽減策:スマート変更登記(職権型)
概要
「検索用情報の申出」をしておくと、住所等の変更の事実を法務局が確認し、職権で変更登記を行います。これにより、申請不要・登録免許税不要となります。申出は無料です。
検索用情報の申出がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合であっても、それは正当な理由とされ、過料の適用対象となることはありません。
申出方法
- 新しく登記名義人になるときに同時申出:所有権保存や移転登記の申請書に、氏名(ふりがな)・生年月日・メールアドレス等を併せて記載
- 既存の登記名義人の申出:令和7年4月21日以降、オンライン(かんたん登記申請)または書面(法務省公表の申出書式)で提出可能
職権登記の流れ(自然人の例)
- 法務局が定期的に住基ネットに照会して、住所・氏名の変更を把握
- 法務局から、申出時に登録したメールアドレスに変更登記を職権でしても良いか確認メールが送信される
- 本人が承諾すると、職権で住所等変更登記を実施(登録免許税不要)
まとめ
住所等変更登記の義務化は、
- 変更日から2年以内の申請義務
- 正当な理由のない不履行への過料(5万円以下)
- 施行日前の変更に対する猶予(令和10年3月31日まで)
- 検索用情報の申出に基づくスマート変更登記で申請不要・費用不要
という4点が柱です。早めの準備と「スマート変更登記」の活用が、将来の手続を円滑にし、リスク回避につながります。
参考文献
法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。
ABOUT ME